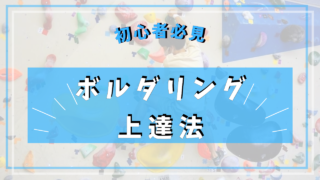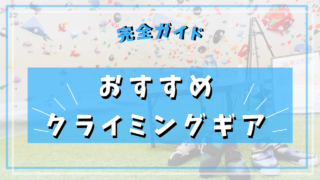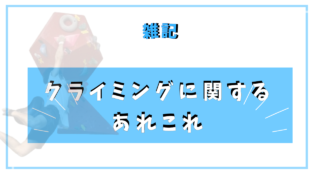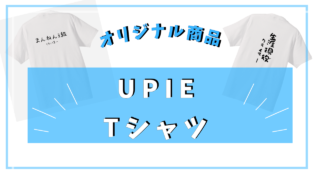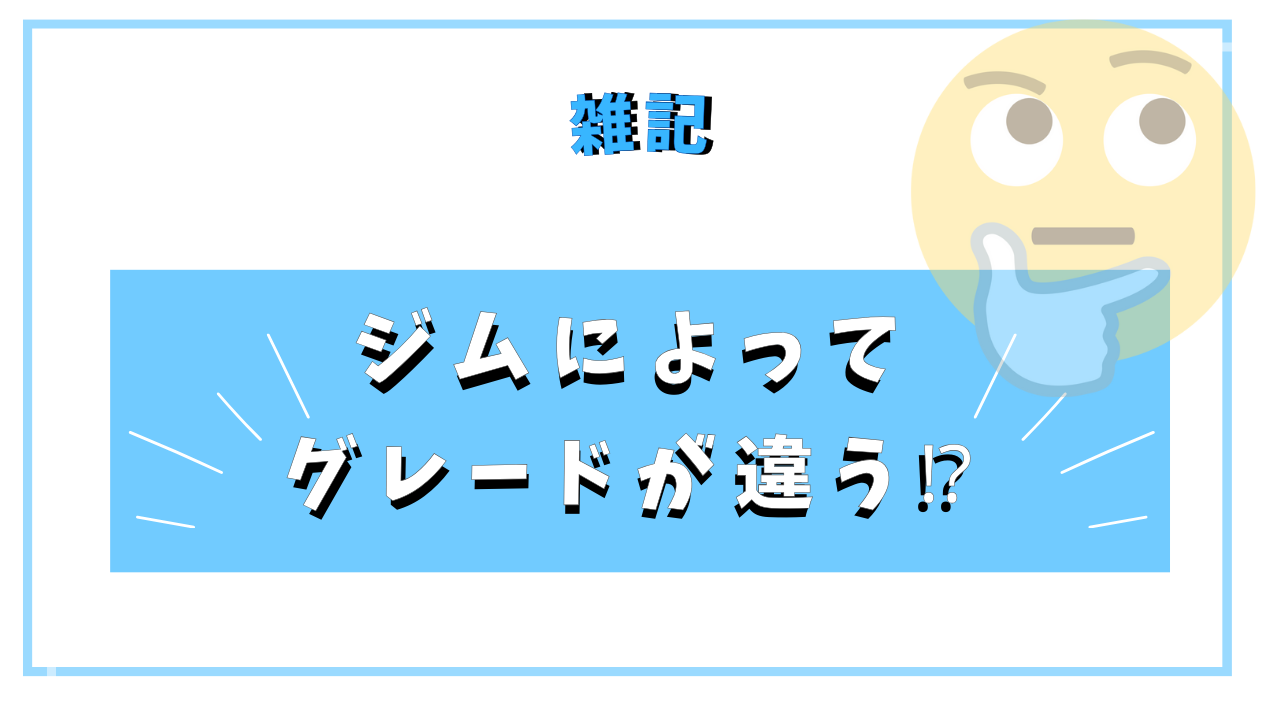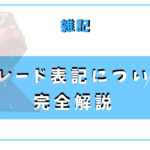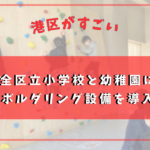あれ⁉グレードがなんか違う…
クライミングジムに足を運ぶと、壁には様々な色のテープが貼られており、それぞれが異なるグレードを示しています。しかし、あるジムで簡単だと感じたグレードが、別のジムでは難しいと感じることがあります。これはなぜでしょうか?
ジムごとのグレードの違い
ジムによって、ルートセッティングのスタイルやターゲット層が異なるため、グレードの感覚に差が出ることがあります。例えば、あるジムでは初心者をターゲットにしているため通常よりも甘めなグレードで設定していたり、ターゲットが上級者の場合は難しめのグレードになっていたりします。また、子供が多いジムでは距離感が短くなっていたりします。そのためジムによってグレードに差がでます。
東京のジムで甘め設定のジムはノボロック。
辛めの設定のジムは荻パンなど。

初めていつもと違うジムに行くとあれっいつも登れているグレードが登れないなんてことがありますが、あくまでグレードはジムごとに違うことを覚えておきましょう。
グレードは誰が決めるのか?
クライミングのグレードは、そのルートを設定したセッターの主観によって決定されます。セッターは自身の経験や感覚に基づき、ルートの難易度を評価します。そのため、セッターによって、同じグレードでも難易度にブレが生じることがあります。
グレードはあくまで目安
レードはあくまで目安であり、クライマーの体力や技術、岩の種類や条件によって感じる難易度は異なります。そのため、ジムや岩場ごとで難易度に大きな差が生まれることを理解し、自分に合ったチャレンジを見つけることが大切です。
グレードの違いを楽しむ
異なるジムでのクライミングは、新しい発見や学びがあります。グレードの違いを楽しむことで、自分のクライミングスキルを多角的に磨くことができます。また、様々なスタイルのルートを試すことで、よりバランスの取れたクライマーになるでしょう。
クライミングジムでのグレードの違いは、クライミングの多様性と個性を反映しています。グレードに縛られず、自分のペースで楽しみながら上達を目指しましょう。
この記事では、クライミングジムにおけるグレードの違いについて掘り下げ、クライマーが直面するこの現象を理解するための情報を提供しています。クライミングの楽しさと共に、グレードの違いを受け入れ、それを自分の成長の機会として捉えることが重要です。安全に注意して、クライミングをお楽しみください!
オリジナルTシャツ
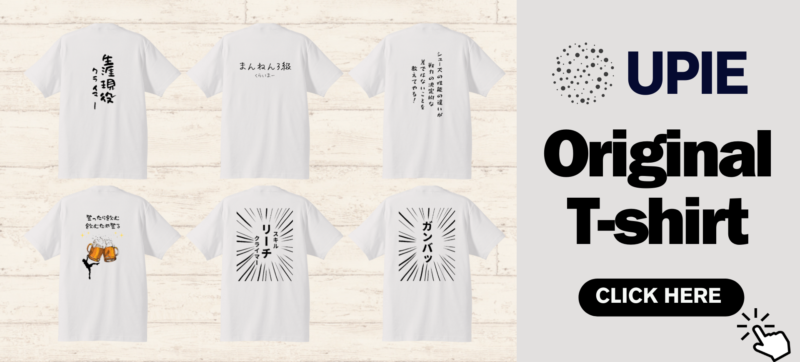
上記をクリック↑↑